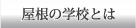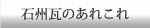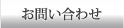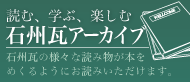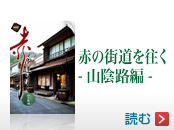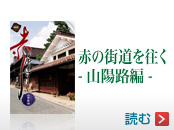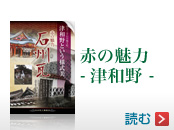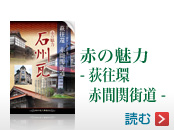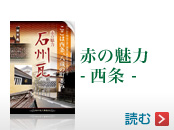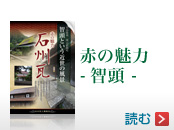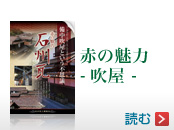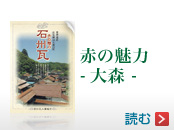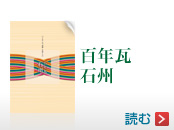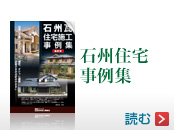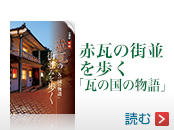慶長5年(1600年)関が原の戦いで東軍に味方して勝利を収めた坂崎出羽守によって築かれた城下町である。坂崎家はいわゆる千姫事件で失脚、元和3年(1617年)因幡の鹿野城主であった亀井政矩は入府し、以後明治維新までの250年間にわたって津和野藩4万3千石を収めました。
慶長5年(1600年)関が原の戦いで東軍に味方して勝利を収めた坂崎出羽守によって築かれた城下町である。坂崎家はいわゆる千姫事件で失脚、元和3年(1617年)因幡の鹿野城主であった亀井政矩は入府し、以後明治維新までの250年間にわたって津和野藩4万3千石を収めました。
初代政矩は、産業振興に力を入れ、特に和紙の生産を奨励。4万3千石の小藩であったが実質15万石という経済力を持つまでになります。現在、石州半紙は国の重要無形文化財に指定され、日本有数の和紙として世界でも人気を集めています。
城と城下町は、坂崎出羽守によって16年にわたって、典型的な近世城下町として整備され、町内用水路など見事な町造りがなされています。
 |
 |
 |
 |
街の周辺に今も残る段々状の畑は、家老多胡主水の名をとって主水畑と呼ばれ往時の産業振興の基盤整備を偲ばせる風景です。
津和野の城下町は、JR津和野駅の東南にあたる殿町を中心にして本町、祇園町、魚町、久保町、稲成町などへひろがっています。造り酒屋をはじめ殆どの家が伝統的な和風の佇まいで、落ち着いた城下町がそのまま現代によみがえったかのようです。
津和野の伝統的な民家は、切り妻つくり、中二階建てもしくは二階建て、平入りで石州瓦の赤と白漆喰の袖壁、虫籠窓や格子窓が、やさしく調和しています。
 |
 |
 |
 |